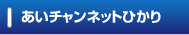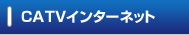CATVインターネットの接続 用語解説
- IPアドレス
- インターネットに接続しているコンピュータやルータなどを識別するために割り振られる数値。255までの数字4組を「.」で区切ったものになる。0から255までのアドレスを4組に区切って使用するところからIPv4アドレスとも呼ばれる。
- グローバルアドレス
- インターネットに接続した端末の識別に使うIPアドレスであり、世界に2個とは同じ物が存在しないIPアドレス。その為、このIPアドレスを持っていない環境下からのインターネットへの接続は不可能となる。また、通常使用されているIPv4と呼ばれる規格のIPアドレスは全世界で約40億個程度しかなく、その管理はNICと言う団体が行っている。近年この規格が枯渇状態になってきており、IPv6と言う新しいIPアドレスの規格が運用されつつある。
- プライベートアドレス
- 個別のネットワーク(ローカルネットワーク)内にある端末の識別に使用するIPアドレス。通常は、会社内や家庭内に複数のパソコンをネットワークに接続する時などに、ブロードバンドルーターより割り当てを行われる際に使用されるケースが多い。
- MACアドレス
- LANカードやルーター、モデム等のネットワーク機器内にある固有端末を表すアドレス。ケーブルモデム本体は、接続先となるLANカードやルーター等のMACアドレスを自動的に接続先として認識(認証)し動作する。
- ケーブルモデム
- ケーブルテレビ網を利用して、データ伝送を可能にするモデム。電話回線を使ったダイヤルアップモデム、TAと言う機器を使用したISDN、従来型メタル電話回線を使用したADSLモデムと比較して、ケーブルテレビ回線ならではの比較的高速な安定した通信速度で接続ができる。
- イーサネット(Ethernet)
- LANの伝送規格のひとつで、現在もっとも普及している方式。LANの接続形態によって、10BASE-T、100BASE-Tなどの方式がある。最近では、より高速なLAN環境を構築するために、Ethernetの拡張規格で最大伝送速度1000Mbps(1Gbps)の「1000BASE-T」(GIGABitEthernet)も導入されるようになってきている。
- 10/100BASE-T(ジュウ/ヒャク・ベース・ティー)
- Ethernetの接続方式の規格のひとつ。最も多く利用されている。ツイストペアケーブル(より対線)を使う。最大伝送速度は最大10Mbpsまたは100Mbps、1セグメントの最大長は100m。
- プロバイダ
- もともと「供給者」の意味だが、一般にインターネットとの接続サービス提供する業者を指すことが多い。「ISP(Internet Service Provider)」と呼ばれることもある。いちはらケーブルテレビもCATVインターネットのプロバイダということになる。
- ルーター
- 1個のネットワーク接続に使用されるIPアドレスを仮想的にルーター独自のローカルIPアドレスに変換し、1個の大元のIPアドレスで複数のパソコンを同時にネットワークに接続する事の可能な機器。また、ルーターにはLANケーブルを接続する有線式と電波や赤外線等を使用して接続させる無線LAN方式がある。 また、最近のルーター自体には、外部からの不正侵入を防ぐための「ファイアーウォール」と呼ばれるセキュリティ機能を搭載した機種が多い。
- ハブ
- ネットワークで使われる集線装置。10/100BASE-Tなどのネットワークで利用される。一般的にハブはルーターの配下に接続され、複数のパソコンは通常モデムからの信号をルーターを経由し、ハブへ接続され、スター型のネットワークを構成する。もともとの意味は「中心」「中枢」。
1台のハブに接続できる機器の数はそのハブの持っているポートの数によって異なり、5ポート、8ポート、16ポートなどのハブがパソコンショップ等で販売されている。ポート数については、使用パソコン台数以上のポート数を選択する必要がある。
伝送されるデータのあて先によって振り分けを行うスイッチングハブなどの高機能なハブもある。 - WWWブラウザ
- WWWで提供されるWebページを閲覧するためのソフトウェア。最近では単に「ブラウザ」と呼ばれることも多い。代表的なものに米マイクロソフト社の「InternetExplorer」や、オープンソースプログラムMozila系の「FireFox」、Apple社の「safari」等がある。
- CGI
- 「Common Gateway Interface」の略。Webページから外部プログラムを呼び出し、その結果をWebページに反映させるための仕組み。Webページで見かけるアクセスカウンタやアンケートフォームなどでよく利用されている。
- セキュリティプログラム
- パソコンを不正プログラム(マルウェア)と呼ばれる、ウィルスやスパイウェア等の悪質なプログラムから守る為のプラグラムの総称。尚、セキュリティプログラムは常に最新の更新(アップデート)を行い、最新の不正プログラムからパソコンを常に守れる状態にしておく必要がある。最新の状態に無い場合や、セキュリティソフトの有効期限切れのままの状態では、不正プログラムからの防御能力は極めて低下し、パソコンが不正プログラムに感染しやすくなる。
- ウィルスプログラム
- 不正プログラム(マルウェア)を分類する上での一つの大きな種類の総称。このウィルスプログラムと呼ばれる分類については、パソコンが感染した場合、そのパソコン内のデータ・プログラムの破壊・改ざんや、不特定多数のパソコンやサーバーに対する攻撃を行ったりする悪質なプログラムを指す。感染経路としては、インターネットやネットワーク上からの直接感染、感染パソコンからコピーしたデータをCD、DVD、USBメモリー等の外部記憶媒体を通じ感染する媒介感染等の経路があり、また、ファイル共有ソフト経由感染や感染ホームページを閲覧した事による感染、電子メール上からの感染等々、感染経路については多岐にわたる。感染した場合、感染したウィルスの種類により症状は異なるが、多くは、パソコン自体の動作が遅くなったりエラーが多発する様になる。一度感染すると通常のセキュリティプログラムでは駆除が不可能な状態となり、最悪パソコンの初期化作業が必要となるケースが多い。また、感染直後はそのパソコン使用者が気付かないケースも多々ある。防御するには、セキュリティプログラムの導入及び、セキュリティプログラム及びOSを常に最新の状態への更新(アップデート)が必要となる。
- スパイウェアプログラム
- 正プログラム(マルウェア)を分類する上での一つの大きな種類の総称。このスパイウェアプログラムと呼ばれる分類については、パソコンが感染した場合、感染パソコン内に記憶されている個人情報的なデータ(電子メールアドレス、ユーザーID、パスワード、クレジットカード番号等)を特定の悪質者へ、使用者が意識しないパソコンの動作領域であるバックグラウンドで、感染パソコンから抽出した個人データを自動送信すると言う行動をする。感染経路としては主に、著作権を侵害している動画・音楽等の違法ダウンロードサイトや、アダルト系サイトにアクセスした事により、それらのデータをパソコン上に表示したと同時にパソコン内にスパイウェアを仕掛けられてしまうと言う経路が最も多い。感染した場合、スパイウェアが活動を始めるとパソコンの動作が遅くなったり、ある日を境に迷惑メールが多数送信されたりと言った症状が発生する。スパイウェアからの感染を防止するには、ウィルスと同様にセキュリティソフトの導入及び最新の状態に常に更新する事が必要となる。
- BOT系ウィルス
- 現在、非常に多くの亜種が日々発生している不正プログラムの種類の総称。このBOTウィルスと呼ばれる分類については、感染したパソコンをそのBOTウィルスをばら撒いた悪質者がインターネット回線を通じて操り(リモートコントロール)し、感染パソコンをロボット化する事から、BOTウィルスと総称されている。感染したパソコンは、その悪質者により操られ、第3者所有のサーバーやパソコンへの攻撃(無作為攻撃や特定攻撃)を行ったり、また感染パソコン内の個人データを盗んだりと言ったスパイウェアの様な働きを行う事から、最近では、ウィルスとスパイウェアとは別の種類に区分けされた不正プログラムの存在として、BOTウィルスと言う位置づけをされる事が多い。感染経路としては、通常のウィルスやスパイウェアと同様の感染経路もあるが、多くはOS(Windows)自体のプログラム的欠陥(セキュリティホール)を突くネットワーク系感染が多い。このOSのセキュリティ上のプログラム的欠陥を攻撃する。その為、これらのBOTウィルスからパソコンを守るには、セキュリティソフトの導入、セキュリティソフト及びOSを最新の状態への更新及び、更に物理的なセキュリティとなるブロードバンドルーターの導入も効果的である。